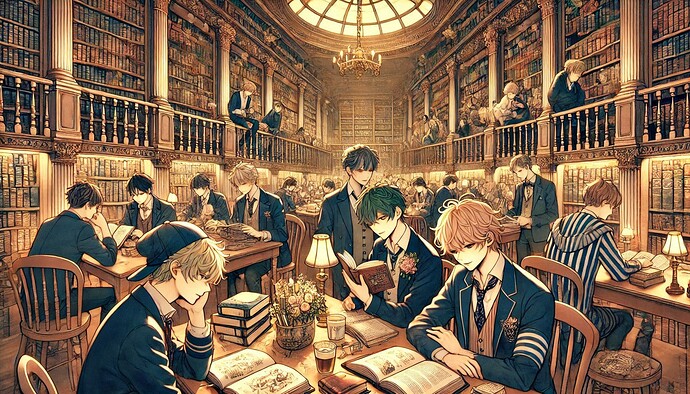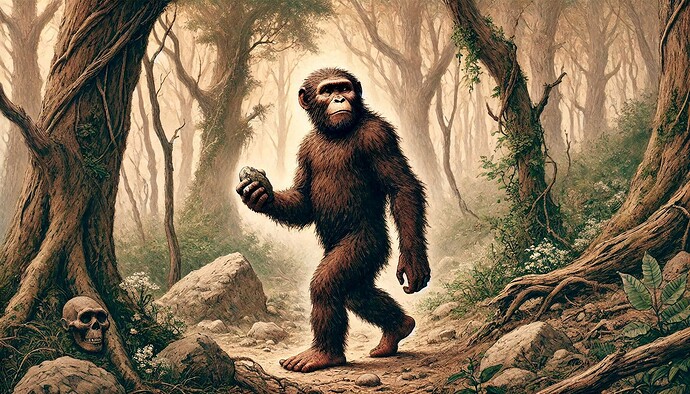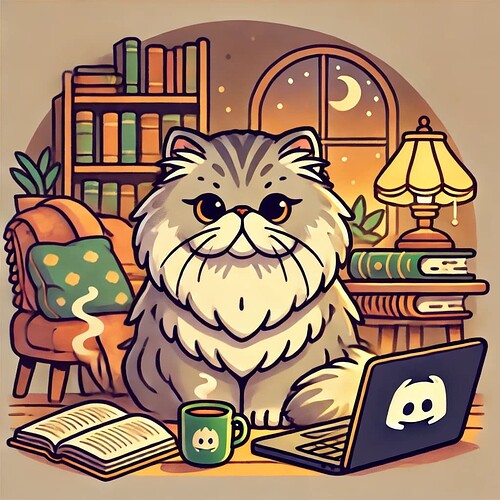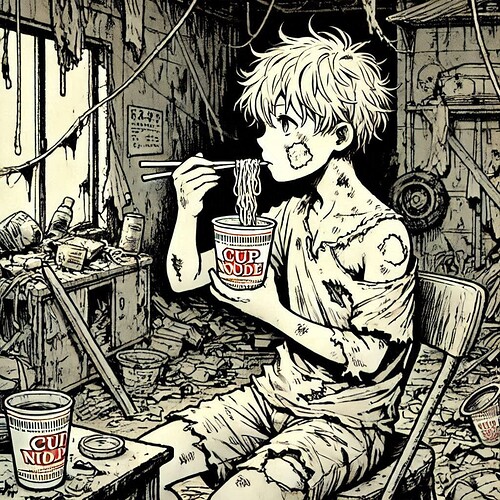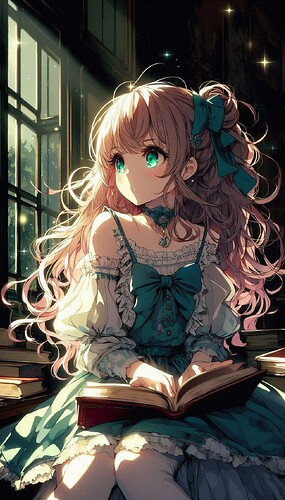なんか、ディスコードを混ぜるように指示すると、そこはかとなく、ディスコードのロゴ(Clydeくんという名前らしい)に寄せてきてる感じがしますねw特に目がClydeくんではないかとw
年末、混みすぎ、サーバーダウン。(●^o^●)
OPEN
いろいろな勉強についてのディスカッション用チャットグループを作りました。数学やら哲学やら、そのほかいろいろな科目について、問題を見て話し合ったり、哲学的思索を深めたり、あるいはただ作業しながら雑談していたりします。
興味がある方は、 @Komori までDMください。あるいはここで返信してくださってもOK。
↓のような数学問題についての雑談がいまのところ多いですが、各々の好きな勉強について語ったり、勉強の成果を報告したり、ただ単に作業のお供にしたり、気楽に参加してください。
現在二名が参加中です。ただいまの勉強科目は、ギリシア哲学、地理、英語、数学。
米国にある祭りのゲームで、参加者が離れた位置からコインをはじいて、机上に置かれた1インチ四方の台座に乗せるという遊びがある。
コインがはみ出ずに台座に乗ったら、賞金として5セントがもらえるのである。(このとき掛け金1セントは戻らない)
コインがはみ出てしまったり、台座から落ちたら掛け金没収、参加者の負けである。
さて、銭形くんはコイン投げの名手で、台座から落ちることの無いようにコインをはじくことが出来るという。
いま、1セントコインの直径が4分の3インチとすると、銭形くんの勝率はいくらになるだろうか。
追記
訳の修正。失礼仕った
Chuck-a-Luckという賭けのゲームがある。
プレイヤーは1から6までの六つの数字のうち、ひとつを選んで賭けることが出来る。
三つの六面サイコロを振って、もし賭けた数字が出たら、その個数に応じて賭け金が戻ってくるという内容である。
賭けた数字が
1個出たら、賭け金の同額と、もともとの賭け金が。
2個出たら、賭け金の二倍と、もともとの賭け金が。
3個出たら、賭け金の三倍と、もともとの賭け金が。それぞれ戻ってくる。
もちろん、1個も出なければ賭け金は没収される。
賭け金をnとすると、賭け一回につき、平均してどの程度の儲けが望めるだろうか?
同一の平面上に三点がある。そのすべてを通る直線はないという。この三点に対して等距離にある直線は何本引けるだろうか。
アウストラロピテクスと指示するとでてくる。実際のところは、たぶんもうほんの少し人間に似た顔で、もうほんの少し体毛が薄いんじゃなかろうか。腕や脚、手の大きさなども、やはりAIで上手く表現するのはむずかしい。
生きていた数百万年のあいだに猿人全体もいろんな変化を遂げているから、さらに細かく表現しようとするとやっぱり手描きになるねえ。
絵描きってすげえな。
GPTの制限がようやく解除されたので、猫ちゃんのイラストをまたお願いしてみました。今度は猫の目に光が入ってるバージョンを生成してくれたみたいで、ディスコードアイコンとしては、黒目がよいのかもしれませんが、ちょっとゾンビなイメージがして、もうちょっと明るい雰囲気がいいかなぁ?と思ったので、猫の目に光が入ってるバージョンをアイコンとしては採用しようと思います。
あと、何枚か似たような猫のイラストを生成してもらって、そこから選びたいですね。
ハリーポッターに出てくる様な、図書館は、叡智に溢れていて、憧憬を感じる。![]()
人類史にまつわる絵も、良いですね。
私は、栄養学の観点から、旧時代の食文化に興味を持っていて、
“貝塚”や“骨髄主食説”などが、
常識的な栄養学への、新たな示唆になりうるのではないかと期待しています。
最後の絵は、『ダンガンロンパ』に出てくる江ノ島盾子に似てると思いました![]()
骨髄主食説というのは初めて聞くね。
猿人の時代から、肉食獣の食べ残しを食べるScavengingの痕跡が化石人骨や食料となった動物の化石骨に見られるのはよく知られているけれど、食糧事情の不安定なその時代でもなお骨髄を主食というのはちょっと考えにくいように思う。猿人以降、新人に至るまで、ヒトが骨髄を食べていたことはおそらく間違いないだろうけれども、それがメインの栄養源になったとは言えるんだろうか(。´・ω・)?
しかしけっこう面白い仮説ではある。
ググったらこんなのも出た