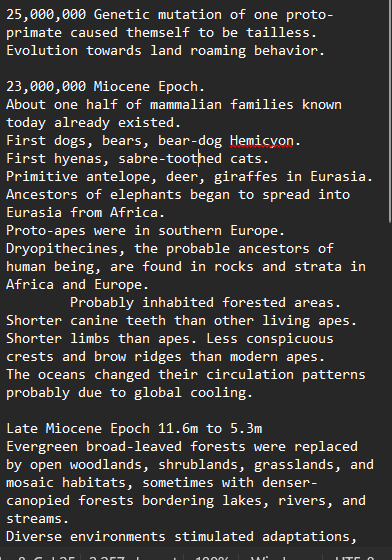ハダカデバネズミの存在を始めて知ったのは、新世界よりっていう、ホラー作家の人が書いた長編小説(ちょっとHなやつで、漫画化やアニメ化もされてます)だったのですが、改めて調べてみると、DNAを残す個体と、残さないで、残す個体のお世話をする係に分業することで、生存と繁殖の効率を上げている、真社会性生物で、昆虫(アリやハチ)には珍しくない形態らしいのですが、哺乳類ではデバネズミ系統ぐらいしか、見当たらないらしいですね。
いちおう、コロニー内の個体はすべて、兄弟姉妹(繁殖用のオスをのぞいて、ほとんどメスらしいですが)で、血縁関係はあり、まったくの赤の他人というわけではないので、一族の生存戦略としては問題ないのでしょう。
自分の直系の子孫をそれぞれが残して、資源を一族内で奪い合うより、一族で役割分担をして、一族全体の繁栄を目指すやりかたは、資源が少ない地域では、最適な戦略といえたのかもしれません。
人類は社会保障制度を作ることで、赤の他人の面倒をみるようになり、地域や一族といった、地縁、血縁に頼らずとも、ホモ・サピエンスという種全体の存続と安定を図ろうとしてきたわけですが、そうなると、役割分担の意識が薄れはじめ、だれもが自分のことしか考えないようになるという弊害がでてきたように思えます。
それが一概に悪いわけではないのですが、結果として、昭和の大家族みたいな、一族主義はすたれ、核家族化がすすみ、(家族という社会の最小単位が維持されていれば、種の保存自体は可能であったが)さらには少子化に見られるように、自らのDNAを後世に残すよりも、個体としての自己の人生を充実させることに、人生のすべてのリソースを使うようになりつつあるのが、現在進行系ですすむ、少子高齢社会の実体だと思われます。
再度いいますが、それが一概に悪いわけではありません。
なぜなら、地球資源には限りがあり、地球資源が尽きるまえに、人類が太陽系外(せめてガスが大量にありそうな木星くらいまでは?)に進出できなければ、人類は滅ぶわけです。
AIや量子コンピュータが当たり前に使われる時代が到来すれば、もはや文明の進歩は人類からAIへと肩代わりされることは必然なわけで、人口を増やして、その中から優秀なDNAがピックアップされることにより、文明の進歩を進めるやり方はもう必要ないわけです。(もうひとつは、資源を巡る争いの中で、戦争という手段により、科学技術の進歩という目的を果たしてきたわけですが、これも資源の浪費以外のなにものでもなくなるでしょう)
AIと量子コンピュータによって、人類自体も次世代は、DNAレベルで宇宙進出に適した個体が生み出されるようになり、いずれは人類とAIが融合する未来もやってくるでしょう。そうなれば、ジョージア・ガイドストーンに書かれていたように、地球に残る人類は5億人程度でも多いくらいなのかもしれません。
イーロン・マスクがアメリカ政府を解体しようとしていますが、彼は火星へ自分が行きたい人間なので、無駄な浪費(優秀なDNAの持ち主以外が生活に使う必要不可欠な資源でさえも)を極力なくして、自分の事業に地球資源と人的資源のすべてを当てようとしているのかもしれません。
自分のDNAを残したい人にとっては、この考えは非常に危険な考えといえるかもしれませんが、(これを21世紀の優生思想と呼びましょうか)DNAをとくに残したくない人間、または残せなさそうな人間にとっては、個体である自らの寿命までの生存が保障されていれば、それで満足できるような気がします。(まぁ、それさえも許さない風潮が出てきているわけですが、DNAを残したい子持ちのみなさまと、残せないw独身者のみなさまの不毛な争いがXなどでも、社会保障制度を巡って争われていて、まぁ、いつの時代も大衆は、イーロンのような上級国民の思惑に踊らされて、分断統治されるものだなぁと半ばあきらめ顔で見ていたりします)
「いいね!」 3
Komori
301
年越しの瞬間の読書箇所
『存在と時間』
What is questioned is to be defined and conceptualized in the investigating, that is, the specifically theoretical, question.
Komori訳
問われる客体は、それを問うて探し求めるうちに定められて来、理が見えて来るものなのだ。それが、形を持たぬものに対する問いであるのならなおさらのことである。
邦訳だとどうなってんだろう。持ってないからわからん。
こういった文章に対してはCopilotでさえ誤訳が目立つ。ひどいね。
哲学書は翻訳機では読めないというのは面白い発見ではあるけれども。
追記
それこそが、きわめて抽象的なるものについて問うということなのである
という訳かもしれん。どっちがいいだろうね。
ドイツ語で読みてえええ。もっと簡単な言葉で書いてよマーティンおじさん
追記2
たぶん追記した訳でよさそうね。
うーむ。英語力を鍛えないといかん。
追記3
なんか最初の訳のような気もしてきた。
最後のquestionのまえのコンマが問題だ。なんでそこなんだ。わからんくなるじゃないの。やあねえもう 
追記4
たぶん追記した訳だな。うん。きっとそうだ。
「いいね!」 1
Komori
302
アリストテレスの英訳文のほうが読みやすいとかちょっと大丈夫かこの本。
マーティンおじさんもうすこしやさしく言ってくれ。
アリストテレスの文章はなんというか、難しい箇所でも一語一語丁寧に丹念に解きほぐせばしっかりと読める感じだったけれども、ちょっとハイデガーは読みにくいなあ。
英語力がないせいですね、はい。精進します。
「いいね!」 1
haru
303
今年の目標は
新しく楽しめることを見つけること。
自分のための学びをすること。
今年は半年間心についての講座を受けにいく。
去年は境界線についての通信講座を受講し始めたので、そのシリーズを残りの半年はやってみようかな。
「いいね!」 4
kuji
305
みんな正月をチヤホヤしとるくせに
あと数日すると節分やバレンタインにあっさり推し変するのは
あんまり薄情じゃあござんせんか
少し愛してなが~く愛して
ですよHigh
「いいね!」 5
Komori
306
昨日は勉強の時にてきとうにメモ帳でノートをとった。(学生時代以来)
メモリーツリー方式というのを学生時代にずいぶん勧められたっけな。
しかし面白いのは、当時と比べても今回のほうがどう振り返っても記憶への定着がよさそうってこと。
ノートの形式よりは、自ら考えてノートとってるかってのが重要そうだね。
学生時代に知りたかったです
黒板書き写すのって無駄やん……もったいない時間を過ごしましたわ。
そしてもう一つ気になるのが、ノートを取るVSその時間分再読する、という勝負のゆくえ。正直どっちがいいんだろうね。
しかし紙のノートっていらんな。
最後までアナログ需要が残るのってたぶん数学だけど、タブレットなら手で計算するのもかんたんだしな……
当時パソコンでノート取ればよかった。ばかだねえ十代のぼくよ
追記
ノートの文法ミス多くて笑う。
もう一回復習だな文法。もっと作文せな
「いいね!」 2
Komori
307
そういえば講義を聴きながらノートってとれないね。さっき講義動画で試してみた。
いや、とれるけれども、あきらかに聴くほうのパフォーマンスが落ちる。そして連動してノートのパフォーマンスも落ちる。
なあんで昔の僕はノートなんてとってたんやろ。おばかねえ。
手を膝の上にのせて目をかっぴらいて聴け、と子供の頃の自分に教えてやりたい。
でもそうか怒られるのかノートとらんと。
子供ってたいへんだなあ……
しかしまあ、教科書にないことを教授が喋ったら一瞬だけその箇所に印を付けるとか、そういうのが最善のように感じる。聴くほうをしっかりせねばなんにもならぬしな。
あるいは講義は全力で聴いて、その後で真面目な子にノート見せてもらう。
ああ、これが最善か……
あんまり考えもせずに暮らしていたのだなあ当時の僕は
動画講義なら一時停止があるし、↑の話に意味なんてないのではあるけれど。
「いいね!」 2
30年くらい前に運転免許をとったんですけど、最初マニュアル免許コースを受講して、右も左もわからず、エンストさせまくってたら、(だいたい初心者がクラッチ操作しながら、ハンドルとペダルも操作しつつ、周りの状況も確認するとか無理でしょw)おじーさん教官からめちゃくちゃ怒られて、辞めたくなりました。
しかし、オートマコースなるものがあったので、まずはそちらを受講して、限定解除すれば?みたいなアドバイスを事務の人に受けて、オートマコースを受講したわけです。教官も変わってもらって、性格はおおざっぱで、人を小馬鹿にした言動をよくする昭和の田舎によくいる中年のおっさん教官だったんですけど、前回のおじーさん教官より、厳しい指導もなく、(教官のいい加減な性格が幸いしたのだろうw)相性もそれほど悪くなかったので、スムーズにオートマ免許を取得できて、限定解除も一回の試験でなんなくクリアできました。
最近は、そういうオラオラ系教官はいないみたいで、少子化と若者の車離れもあるのでしょうが、やさしいスタイルの指導が当たり前の世の中になってるみたいで、本当に羨ましいなぁと思うしだいです。
「いいね!」 5
haru
310
自分は人を引っ張ってくよりも、その人を尊重することを大切にしたいのかもしれない。
「いいね!」 2
haru
311
つべこべ言わずに言われた通りにすれば良い方向に向かうこともあるけど、出来ればその人が納得した上で前に進んでもらいたい。
「いいね!」 1
haru
317
自分は選ぶ立場にある。
医者や病院を選ぶことが出来る。
だからレヴューしていいし、自分には合うか合わないか、こういうところが良い悪いと思ったなど感想を持っていい。
新しい趣味を見つけるときもそうだよなあ。
「いいね!」 3